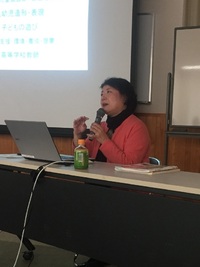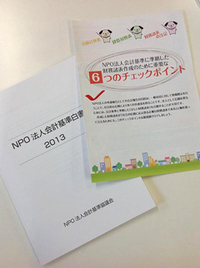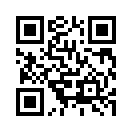2015年11月18日
「想い」を生かせる働き方とは ~NPOの実態と労働環境を考える
NPOで勤務歴9年目の小林です。
15日は「NPOで働く」を考えるセミナーを開催。NPOのスタッフや理事、学校の先生や高校生3年生も参加しました。
前半は、浜松、名古屋のNPOで働く20~40代のスタッフが、NPOで働くようになった経緯、NPOで働くやりがいと大変さ、活動と労働の線引きについてパネルディスカッション。
きっかけは、リーマンショックで首になった ことだったり、会社勤めをしながらボランティア
ことだったり、会社勤めをしながらボランティア として関わっていたことで声がかかったり、緊急雇用があって手伝っていたNPOに雇用されたり…と様々。働き方もフルタイムだったり、他の仕事と兼業だったり。
として関わっていたことで声がかかったり、緊急雇用があって手伝っていたNPOに雇用されたり…と様々。働き方もフルタイムだったり、他の仕事と兼業だったり。
やりがいは、企業では組織の一員として決まった仕事をするだけだったけれど、自分で企画したり 、仲間と共に「こうなったらいいな
、仲間と共に「こうなったらいいな 」を実現することができる、それまでの職場では話題にもならなかった社会的な課題について話すことが増えて社会勉強にもなっている、NPOでは男女の役割分担や年功序列に関係なく働ける、組織が未整備だからこその「創っていく」楽しさ
」を実現することができる、それまでの職場では話題にもならなかった社会的な課題について話すことが増えて社会勉強にもなっている、NPOでは男女の役割分担や年功序列に関係なく働ける、組織が未整備だからこその「創っていく」楽しさ がある、そんな話がでました。
がある、そんな話がでました。

一方で大変なことは、やはり身分や待遇が不安定 なこと。また「育ててもらう」ことが期待できないこと、やりたいことが大きく膨らみすぎ
なこと。また「育ててもらう」ことが期待できないこと、やりたいことが大きく膨らみすぎ て自分で自分の首をしめてしまうこと…などが出ました。
て自分で自分の首をしめてしまうこと…などが出ました。
それは「活動か?仕事か?」の線引きにも関わってきて、休日のイベント参加などは自分自身のためにもなるから「活動(=無報酬)」でも気にならない人がいる一方、ボランティアと有償スタッフとの違いはドライに割り切って、活動は「行きたいと思えない時は休む!」という人もいました。オーバーワーク についても自分で管理しないといけないということですね。
についても自分で管理しないといけないということですね。
ボランティアから入ったスタッフは、労働も活動(=自発的、やりたいこと)の延長に位置づけられる人が多いと思うのですが、稼ぐために就労している人にとっては、無報酬=強制?=ブラック労働??になりかねません。この線引きは人によって随分異なるので、雇用する側は気をつけなくてはいけない部分です。
NPOで働くことをキャリアとして活かせるか?という問いについては、企画する力やプロジェクトを運営する力、交渉したりコミュニケーションをとったりする力はNPOではとても鍛えられるので、様々なスキルとして売り込むことができるのでないか。起業する力がついた、という発言もありました。
まだまだ社会的な地位や評価は高くないかもしれないけれど、売れる強みは持っている! という若者たちの発言は頼もしかったです。NPOの現場で専門性を養って士業になった人もいました。
という若者たちの発言は頼もしかったです。NPOの現場で専門性を養って士業になった人もいました。
3人の話だけでも、NPOの多様な働き方、考え方が見えてきましたが、実費か/謝金か、最低賃金以上か/最賃以下か、自発的で柔軟性があるか/指揮命令系統や規定があるかによって、「労働者」「ボランティア」の捉え方、扱い方が変わってきます。
保険等が払えないから雇用でなくて謝金で、という話は時々ききますが、その“有償ボランティア”、違法になってませんか? という状況もあるので、注意が必要です。
という状況もあるので、注意が必要です。
後半は、特定社会保険労務士の家村先生に制度についてお話しいただきました。労働に関する法律は数多くあり、労働者性の捉え方も違うとのこと。工場労働者を想定していた部分も多いので、NPOのような多様な働き方に合わせるには法改正が必要、というお話でした。
NPOの労働はまだまだ課題がたくさんあって、簡単には解決できないことも多々あります。市場性がある事業(スポーツクラブなど対価が得られるもの)や制度による事業(介護や障害者支援)は収入が安定的なので、比較的安定した雇用が実現できますが、単年度の委託や助成金でやりくりしている団体は、雇用の資金と人の確保はホントに頭の痛い問題 です。
です。
若くて優秀な人材がNPOの現場で持続的に働けることができることが、NPO活動の底上げにもつながっていくので、持続可能な働き方や雇用の方法については引き続き議論していきたいと思っています。
浜松でもNPOで働くスタッフのネットワークが欲しい という声も届いています。 浜松でも作る?
という声も届いています。 浜松でも作る?
今回は、名古屋のNPOスタッフでつくる「東大手の会」との共催。名古屋でも12月9日(水)19時~21時に「NPOのキャリア形成と労働法を考えるセミナー」を共催します。こちらでは、NPO職員のキャリア形成について議論し、今後のあり方について考えます。
どうぞよろしくお願いします!
15日は「NPOで働く」を考えるセミナーを開催。NPOのスタッフや理事、学校の先生や高校生3年生も参加しました。
前半は、浜松、名古屋のNPOで働く20~40代のスタッフが、NPOで働くようになった経緯、NPOで働くやりがいと大変さ、活動と労働の線引きについてパネルディスカッション。
きっかけは、リーマンショックで首になった
 ことだったり、会社勤めをしながらボランティア
ことだったり、会社勤めをしながらボランティア として関わっていたことで声がかかったり、緊急雇用があって手伝っていたNPOに雇用されたり…と様々。働き方もフルタイムだったり、他の仕事と兼業だったり。
として関わっていたことで声がかかったり、緊急雇用があって手伝っていたNPOに雇用されたり…と様々。働き方もフルタイムだったり、他の仕事と兼業だったり。やりがいは、企業では組織の一員として決まった仕事をするだけだったけれど、自分で企画したり
 、仲間と共に「こうなったらいいな
、仲間と共に「こうなったらいいな 」を実現することができる、それまでの職場では話題にもならなかった社会的な課題について話すことが増えて社会勉強にもなっている、NPOでは男女の役割分担や年功序列に関係なく働ける、組織が未整備だからこその「創っていく」楽しさ
」を実現することができる、それまでの職場では話題にもならなかった社会的な課題について話すことが増えて社会勉強にもなっている、NPOでは男女の役割分担や年功序列に関係なく働ける、組織が未整備だからこその「創っていく」楽しさ がある、そんな話がでました。
がある、そんな話がでました。一方で大変なことは、やはり身分や待遇が不安定
 なこと。また「育ててもらう」ことが期待できないこと、やりたいことが大きく膨らみすぎ
なこと。また「育ててもらう」ことが期待できないこと、やりたいことが大きく膨らみすぎ て自分で自分の首をしめてしまうこと…などが出ました。
て自分で自分の首をしめてしまうこと…などが出ました。それは「活動か?仕事か?」の線引きにも関わってきて、休日のイベント参加などは自分自身のためにもなるから「活動(=無報酬)」でも気にならない人がいる一方、ボランティアと有償スタッフとの違いはドライに割り切って、活動は「行きたいと思えない時は休む!」という人もいました。オーバーワーク
 についても自分で管理しないといけないということですね。
についても自分で管理しないといけないということですね。ボランティアから入ったスタッフは、労働も活動(=自発的、やりたいこと)の延長に位置づけられる人が多いと思うのですが、稼ぐために就労している人にとっては、無報酬=強制?=ブラック労働??になりかねません。この線引きは人によって随分異なるので、雇用する側は気をつけなくてはいけない部分です。

NPOで働くことをキャリアとして活かせるか?という問いについては、企画する力やプロジェクトを運営する力、交渉したりコミュニケーションをとったりする力はNPOではとても鍛えられるので、様々なスキルとして売り込むことができるのでないか。起業する力がついた、という発言もありました。
まだまだ社会的な地位や評価は高くないかもしれないけれど、売れる強みは持っている!
 という若者たちの発言は頼もしかったです。NPOの現場で専門性を養って士業になった人もいました。
という若者たちの発言は頼もしかったです。NPOの現場で専門性を養って士業になった人もいました。3人の話だけでも、NPOの多様な働き方、考え方が見えてきましたが、実費か/謝金か、最低賃金以上か/最賃以下か、自発的で柔軟性があるか/指揮命令系統や規定があるかによって、「労働者」「ボランティア」の捉え方、扱い方が変わってきます。
保険等が払えないから雇用でなくて謝金で、という話は時々ききますが、その“有償ボランティア”、違法になってませんか?
 という状況もあるので、注意が必要です。
という状況もあるので、注意が必要です。後半は、特定社会保険労務士の家村先生に制度についてお話しいただきました。労働に関する法律は数多くあり、労働者性の捉え方も違うとのこと。工場労働者を想定していた部分も多いので、NPOのような多様な働き方に合わせるには法改正が必要、というお話でした。
NPOの労働はまだまだ課題がたくさんあって、簡単には解決できないことも多々あります。市場性がある事業(スポーツクラブなど対価が得られるもの)や制度による事業(介護や障害者支援)は収入が安定的なので、比較的安定した雇用が実現できますが、単年度の委託や助成金でやりくりしている団体は、雇用の資金と人の確保はホントに頭の痛い問題
 です。
です。若くて優秀な人材がNPOの現場で持続的に働けることができることが、NPO活動の底上げにもつながっていくので、持続可能な働き方や雇用の方法については引き続き議論していきたいと思っています。
浜松でもNPOで働くスタッフのネットワークが欲しい
 という声も届いています。 浜松でも作る?
という声も届いています。 浜松でも作る?今回は、名古屋のNPOスタッフでつくる「東大手の会」との共催。名古屋でも12月9日(水)19時~21時に「NPOのキャリア形成と労働法を考えるセミナー」を共催します。こちらでは、NPO職員のキャリア形成について議論し、今後のあり方について考えます。
どうぞよろしくお願いします!
Posted by ぽけ子 at 14:46│Comments(0)
│市民活動支援