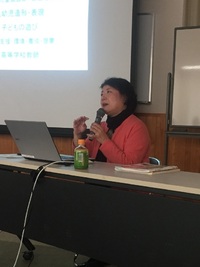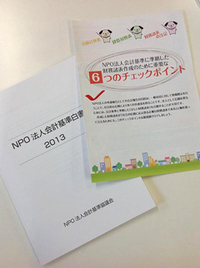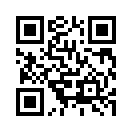2016年11月24日
NPOの災害対策はできているか?
事務局長の小林です。
東京でNPOの会議にいろいろ参加してきたので、報告なぞ。
22日は、昨年の常総水害で茨城NPOセンターの支援の報告会がありました。
日本NPOセンターの声かけで、全国18のNPO支援センターから、のべ189人日、支援に行き、N-Pocketからは私が4日間入りました。
茨城NPOセンター・コモンズの横田さんからは、コモンズが行った活動と現在の活動について報告がありました。
災害が格差や分断を生み、家の解体や空き家化が地域の衰退に影響している。そこで空き家を地域の拠点としてボランティアと共に改装し、事業化して地域住民と共にコミュニティづくりに取り組んでいるとのこと。
それから、緊急期、復旧期、復興期の3グループに分かれて、成果や課題、災害支援におけるNPO支援センターの役割についてディスカッションしました。
私は1ヵ月経った復旧期に入り、ブラジル人被災者の相談や広報に行ったり、外国人を雇用している企業に相談会を打診するなど、主に多文化事業のサポートをお手伝い。復興期に入りつつある時期で、コモンズのスタッフの日常業務にどうつなげていくか?を考えました。
他のみなさんは、災害救援の専門性や経験のある方たちで、被災者の対応やボランティアの活用にも長けていて、N-Pocketは災害救援は素人だし…と思ってました。
でも、NPO支援センターが関わる意味は「災害救援」という新事業ではなく、地域のニーズ調査、地域資源のコーディネートや行政との連絡調整、地域の団体支援といった日常業務の「延長」として考えるべきでは、という話になりました。
また、社協との棲み分けや組織の体力、社協とNPOの復興期の事業の起こし方の違いについても話題になりました。

今後の課題の一つとして、NPOのBCP(事業継続計画)はできているか?と問題提起。
BCPまで行かなくても、緊急時の備えとして、
 事務所内の耐震対策と備蓄
事務所内の耐震対策と備蓄
 スタッフの緊急連絡先(家族との連絡先)把握
スタッフの緊急連絡先(家族との連絡先)把握
 災害時の安否確認の方法
災害時の安否確認の方法
 災害時や暴風などの自宅待機/出勤の判断
災害時や暴風などの自宅待機/出勤の判断
など、どこまで準備していますか?
N-Pocketでは3.11後に整備しましたが、「大地震が来る」と前々から言われている静岡県のみならず、日本全国どこでどんな災害 が起きてもおかしくないので、スタッフを雇用しているNPOは準備の必要がありますよと。
が起きてもおかしくないので、スタッフを雇用しているNPOは準備の必要がありますよと。
ちなみに、先週は隣のNPO法人ARACEと地震の避難訓練がありました。
消防署も来て、消火器の使い方、通報の仕方を練習。外国から来た子たちは、地震の経験がない子もいるし、緊急時の日本語や連絡方法、対処法など学ぶ必要が特にある人たちです。

22日の津波警報では、NHKが「つなみ!にげて!」とやさしい日本語を使い、ふりがなもついて、ユニバーサルになった!と感じました。3.11では、「地図に赤やら黄色が点滅する意味がわからなかった」という外国人が複数いたので、こういう配慮は助かります。
東京でNPOの会議にいろいろ参加してきたので、報告なぞ。
22日は、昨年の常総水害で茨城NPOセンターの支援の報告会がありました。
日本NPOセンターの声かけで、全国18のNPO支援センターから、のべ189人日、支援に行き、N-Pocketからは私が4日間入りました。
茨城NPOセンター・コモンズの横田さんからは、コモンズが行った活動と現在の活動について報告がありました。
災害が格差や分断を生み、家の解体や空き家化が地域の衰退に影響している。そこで空き家を地域の拠点としてボランティアと共に改装し、事業化して地域住民と共にコミュニティづくりに取り組んでいるとのこと。
それから、緊急期、復旧期、復興期の3グループに分かれて、成果や課題、災害支援におけるNPO支援センターの役割についてディスカッションしました。
私は1ヵ月経った復旧期に入り、ブラジル人被災者の相談や広報に行ったり、外国人を雇用している企業に相談会を打診するなど、主に多文化事業のサポートをお手伝い。復興期に入りつつある時期で、コモンズのスタッフの日常業務にどうつなげていくか?を考えました。
他のみなさんは、災害救援の専門性や経験のある方たちで、被災者の対応やボランティアの活用にも長けていて、N-Pocketは災害救援は素人だし…と思ってました。
でも、NPO支援センターが関わる意味は「災害救援」という新事業ではなく、地域のニーズ調査、地域資源のコーディネートや行政との連絡調整、地域の団体支援といった日常業務の「延長」として考えるべきでは、という話になりました。
また、社協との棲み分けや組織の体力、社協とNPOの復興期の事業の起こし方の違いについても話題になりました。
今後の課題の一つとして、NPOのBCP(事業継続計画)はできているか?と問題提起。
BCPまで行かなくても、緊急時の備えとして、
 事務所内の耐震対策と備蓄
事務所内の耐震対策と備蓄 スタッフの緊急連絡先(家族との連絡先)把握
スタッフの緊急連絡先(家族との連絡先)把握 災害時の安否確認の方法
災害時の安否確認の方法 災害時や暴風などの自宅待機/出勤の判断
災害時や暴風などの自宅待機/出勤の判断など、どこまで準備していますか?
N-Pocketでは3.11後に整備しましたが、「大地震が来る」と前々から言われている静岡県のみならず、日本全国どこでどんな災害
 が起きてもおかしくないので、スタッフを雇用しているNPOは準備の必要がありますよと。
が起きてもおかしくないので、スタッフを雇用しているNPOは準備の必要がありますよと。ちなみに、先週は隣のNPO法人ARACEと地震の避難訓練がありました。
消防署も来て、消火器の使い方、通報の仕方を練習。外国から来た子たちは、地震の経験がない子もいるし、緊急時の日本語や連絡方法、対処法など学ぶ必要が特にある人たちです。

22日の津波警報では、NHKが「つなみ!にげて!」とやさしい日本語を使い、ふりがなもついて、ユニバーサルになった!と感じました。3.11では、「地図に赤やら黄色が点滅する意味がわからなかった」という外国人が複数いたので、こういう配慮は助かります。