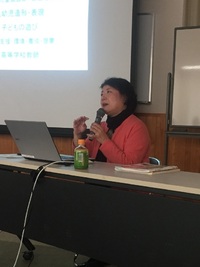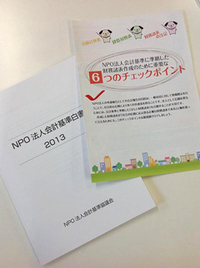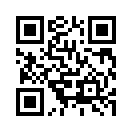2018年08月17日
NPOとして社会に果たせる役割は
行政の協働相手として重要な位置にいるようになったNPOですが、今年3月に静岡県西部NPO法人会と浜松市市民協働地域政策課と協働で浜松市内249のNPO法人に対し、アンケート調査を行いました。107団体から回答があり、43%の回収率。その結果を少しご紹介します。
◆ NPO法人数の推移

このグラフは、NPO法が施行された1998年12月以後、浜松市を拠点とするNPO法人として認証された年ごとの数です。2018年5月現在で市内NPO法人の設立数は309に及びますが、残っている法人は249。60法人が解散や認証取り消しでなくなってしまいました。(各年の二本の棒線の差が消えたNPO法人数を表す)
2006年から2008年度にかけて設立法人数が増えているのは、障害者自立支援法という新体系に移行したことの影響が大きく、障害のある本人やその家族、支援者たちが強い思いで作り上げてきた小規模授産所が法人化を進めたからです。
また、一転して2008年から減少しているのは、公益法人改正をきっかけに、取得しやすい一般社団等の法人格を選択する団体が増えたためです。2015年あたりから右下がり状態が続いていますが、この傾向は全国的にみられます。
次に区別にみてみます。浜松市中区は人口からみても法人数は一番ですが、1万人当たりで見てみると、なんと人口が減り続けている天竜区が群を抜いています。

人と動物の共生問題や山の自然保護と文化の継承、さらに高齢者福祉などに取り組む団体など天竜区を事務所とするNPOが2011年以後、次々と立ち上がりました。どんなNPOがどんな活動をしているのか目を向けることは、地域ごとの課題を市全体で共有するためにとても大切なことだとよくわかります。当事者ならではの目線で課題を見つけ、その解決のため市民自らが立ち上がって活動をしていることが多いからです。
例えば、ある団体は鳥獣の商品化やジビエ文化の普及を行う事業として「ジビエで山の村を元気に!プロジェクト」を実施しており、複数のNPOと協働して商品開発を試みたり、多様なイベントを開いて天竜区を盛り上げていますが、天竜区においては2015年夏を最後に新しいNPO法人ができていないことが気がかりです。
◆ NPOの役割
公平性などを行動原理とする行政や、利益をあげなければならない企業は、社会的課題を解決することについての限界が生じている状況もある中、柔軟性と機動力を強みとする市民団体は社会を支えるセクターとしてどのような役割を担っているのでしょう。市民主体の社会ですから、当然行政に任せきりにしない、まちづくりの主体者としての姿勢が必要です。
小規模授産所が法人化を進めて国の障害者施策を支える活動を継続しています。これはセーフティネットの維持を図っている(サービス提供・事業実施)具体例としてあげられます。
また、ある環境系のNPOでは、防潮林づくりのために企業や学校、一般市民たちに声をかけ、植樹作業を続ける中で、自分たちの住む町のあり方を考え、活動できるようにしています。まさに、市民が自分たちの社会の環境をよりよくしようと、コミュニティづくりの主体者として活動する場を提供しています。
また、食料廃棄の一方で食べ物を食べられない人々が存在する矛盾を解決する方策としてフードバンクを始めたNPOも出ています。儲けを出さなければならない企業には手を出しにくい活動で、これは社会サービスのパイオニアとしての役割を果たしており、このような社会変革のための「新しい価値の創造」は非営利だからこその動きです。
さらに、提言活動は、決して反政府、反企業といった対立の構図ではなく、見えにくいニーズを発見し、その解決のために公共政策としてとりあげるよう、論理的かつ科学的に代替案を示すもので、現場にいるNPOならではの活動です。

アンケートで行った「あなたのNPOが果たしている役割は何か」という設問について、どの年代のNPOも約90%がサービス提供を行っていると回答があったのですが、創成期と最近のNPOの傾向に変化がみられるものがありました。「価値創造」です。現場で事業を淡々と続ける中で見えてくる新しい社会的課題があります。その解決のためにも必要な新しい価値創造に関心を持つ度合いが減ってきているのです。このことは、ソーシャルイノベーションを起こす意気込みの減少ともとれ、気になるところです。行政がNPOを単なる事業実施者としてみるようになっている現実もあり、NPOとして社会に果たせる役割とは何か、を再び考える時期に来ているのではないでしょうか。
◆ NPO法人数の推移

このグラフは、NPO法が施行された1998年12月以後、浜松市を拠点とするNPO法人として認証された年ごとの数です。2018年5月現在で市内NPO法人の設立数は309に及びますが、残っている法人は249。60法人が解散や認証取り消しでなくなってしまいました。(各年の二本の棒線の差が消えたNPO法人数を表す)
2006年から2008年度にかけて設立法人数が増えているのは、障害者自立支援法という新体系に移行したことの影響が大きく、障害のある本人やその家族、支援者たちが強い思いで作り上げてきた小規模授産所が法人化を進めたからです。
また、一転して2008年から減少しているのは、公益法人改正をきっかけに、取得しやすい一般社団等の法人格を選択する団体が増えたためです。2015年あたりから右下がり状態が続いていますが、この傾向は全国的にみられます。
次に区別にみてみます。浜松市中区は人口からみても法人数は一番ですが、1万人当たりで見てみると、なんと人口が減り続けている天竜区が群を抜いています。

人と動物の共生問題や山の自然保護と文化の継承、さらに高齢者福祉などに取り組む団体など天竜区を事務所とするNPOが2011年以後、次々と立ち上がりました。どんなNPOがどんな活動をしているのか目を向けることは、地域ごとの課題を市全体で共有するためにとても大切なことだとよくわかります。当事者ならではの目線で課題を見つけ、その解決のため市民自らが立ち上がって活動をしていることが多いからです。
例えば、ある団体は鳥獣の商品化やジビエ文化の普及を行う事業として「ジビエで山の村を元気に!プロジェクト」を実施しており、複数のNPOと協働して商品開発を試みたり、多様なイベントを開いて天竜区を盛り上げていますが、天竜区においては2015年夏を最後に新しいNPO法人ができていないことが気がかりです。
◆ NPOの役割
公平性などを行動原理とする行政や、利益をあげなければならない企業は、社会的課題を解決することについての限界が生じている状況もある中、柔軟性と機動力を強みとする市民団体は社会を支えるセクターとしてどのような役割を担っているのでしょう。市民主体の社会ですから、当然行政に任せきりにしない、まちづくりの主体者としての姿勢が必要です。
小規模授産所が法人化を進めて国の障害者施策を支える活動を継続しています。これはセーフティネットの維持を図っている(サービス提供・事業実施)具体例としてあげられます。
また、ある環境系のNPOでは、防潮林づくりのために企業や学校、一般市民たちに声をかけ、植樹作業を続ける中で、自分たちの住む町のあり方を考え、活動できるようにしています。まさに、市民が自分たちの社会の環境をよりよくしようと、コミュニティづくりの主体者として活動する場を提供しています。
また、食料廃棄の一方で食べ物を食べられない人々が存在する矛盾を解決する方策としてフードバンクを始めたNPOも出ています。儲けを出さなければならない企業には手を出しにくい活動で、これは社会サービスのパイオニアとしての役割を果たしており、このような社会変革のための「新しい価値の創造」は非営利だからこその動きです。
さらに、提言活動は、決して反政府、反企業といった対立の構図ではなく、見えにくいニーズを発見し、その解決のために公共政策としてとりあげるよう、論理的かつ科学的に代替案を示すもので、現場にいるNPOならではの活動です。

アンケートで行った「あなたのNPOが果たしている役割は何か」という設問について、どの年代のNPOも約90%がサービス提供を行っていると回答があったのですが、創成期と最近のNPOの傾向に変化がみられるものがありました。「価値創造」です。現場で事業を淡々と続ける中で見えてくる新しい社会的課題があります。その解決のためにも必要な新しい価値創造に関心を持つ度合いが減ってきているのです。このことは、ソーシャルイノベーションを起こす意気込みの減少ともとれ、気になるところです。行政がNPOを単なる事業実施者としてみるようになっている現実もあり、NPOとして社会に果たせる役割とは何か、を再び考える時期に来ているのではないでしょうか。
(代表理事 井ノ上 美津恵)